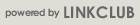11 July
Sometimes I Just Feel Like Smilin' その後
さて、原稿も書き終え、明日は久しぶりに大熊ワタルさんのジンタらムータで神戸へ。そして明後日は広島に行く。
ポール・バターフィールド・ブルーズ・バンドの最終アルバム『Sometimes I Just Feel Like Smilin'』だが、先ほど既に愛聴していた日本盤のサンプル盤を聴き直して驚いた。なんとミックスが違っていたのだ。先日オリジナル盤を聴いて驚くのも当たり前のことだ。おそらく、日本盤のミックスはトッド・ラングレン。で、Re-Mixingでクレジットされているフリッツ・リッチモンドがオリジナルのミックス。リッチモンドのミックスはライヴ感重視でリヴァーヴも多く、ホーンセクションが煌びやかだが、各楽器のレベル操作は少ない。ラングレンは燻んだ音だが、楽器毎のレベル操作は細やかとも言える。ライヴ盤後のリリース、そしてセールスへのプレッシャーと希望を考えると、やはり前者が正規と考えるが、ラングレン版とどちらにするかということは、クレジットを鑑みても、最後まで悩んだことなのだろう。が、何かの間違いで日本ではラングレン版がリリースされた。
そして、また驚き。CDはどうなっているのかと、エレクトラの2枚組アンソロジー盤を確認してみる。このアルバムからは2曲しか収録されていないが、リッチモンド・ミックスに近い。驚いたのはそのことではなくて、曲が違うのだ。アンソロジー盤の最終曲「Song for Lee」は間違いで、テッド・ハリスが中心になって作った「Night Child」だ。今頃それに気づくとは間抜けだが、バターフィールドもかわいそうだな。
02:05:54 |
skri |
No comments |
TrackBacks
29 June
Sometimes I Just Feel Like Smilin'
週末は栗コーダーカルテットの録音。先々週も栗コーダーの録音があったのだが、その時はファイルをいただいて、自宅で済ませたが、今回はスタジオにて。スタジオ録音でも一人で演奏することは少なくは無いが、自宅のように全く一人ということはまず無い。今回は栗コーダーのメンバー以外に中尾勘二、太田惠資両氏に会えたのも、嬉しかった。
さて、週明けて今週は久しぶりの原稿仕事。〆切は週末だが、乗ってくると早い。もう3分の2の字数が埋まってしまった。逆に纏めるのが、難しくなりそうだ。なので、一息入れようと街に行く。今回の原稿資料はmp3なので、(というか新譜の音源に対する資料はもうだいぶ前からmp3だ。)正規盤を買うつもりだった。あまりにも素晴らしいのでやはりもっときちんとした音で聴きたかったのだが、コロナ禍の所為か、輸入盤はまだ店頭には無かった。
他のものを買うつもりは無かったのだが、つい中古盤を少しだけ見てみると、バターフィールド・ブルース・バンドの最終作 Sometimes I Just Feel Like Smilin' のU.S.オリジナル盤が安価であるでは無いか。実はこのレコードは当時の国内盤の見本盤を持っていて、結構音が良いと感じていたのだが、一箇所カッティング段階だと思うが、レベルを急に下げた曲があり、まあ、見本盤ならではか、と納得していた。昨年だったか、今年の春に実店舗はやめて通販のみになってしまった鷹の台のビュグラーでこのオリジナル盤らしきものを見かけたのだが、店主も確信が持てぬ、ということで結局買わなかった。
しかし今回のものは確実に1stプレス。レコード中袋がもうジャケットと同じ写真のデザインとポール・バターフィールドのインタビューまである。
家に帰ると、妻が「これ持ってるでしょ、よく聴いているの知ってる」と返してきたので、これこれしかじか、と説明をして、早速かけてみると、彼女が目を丸くするくらい、別物の素晴らしい音だ。リヴァーヴの感触が手に取るようだ。(ちなみに最近またカートリッジはDL-103に落ち着いてしまった。)
このアルバム、内容としては少し散漫だと思っていたのだが、とんでもなかった。バターフィールドとこの頃の中心人物ジーン・ディンウィディの意図は明確でまとめ上げているのがここではよくわかるのだ。
気になるクレジットはRe-Mixing Engineer FRITZ RICHMOND / Mixing TODD RUNDGREN。最終ではリッチモンドがミックスしたのだろうが、わざわざラングレンのクレジットがあるという事は、貢献はかなりあったのだろう。が、私の知るトッド・ラングレンの音よりも華やかだ。
私はオリジナル盤信仰は無いのだが、今回は本当に驚いた。'60年代後期から'70年代前半は技術革新甚だしく、それは英、米、日、もちろん他の国も、相当に差があった事だろう。誰だったか忘れたがアメリカ人のエンジニアが当時のイギリスのマスタリング、カッティング技術に追いつけなかった、みたいな談話を読んだことがある。
結局はアナログのコピー製造なので、当時としては当たり前の仕方がない事実だが、ここにきて今日のCD及びデジタルは手軽にオリジナルに近いので、それは悪くはない。
さて、もう一仕事。
23:10:00 |
skri |
No comments |
TrackBacks
08 February
カセットテープ
1982年頃、私が大学の近くの四畳半一間で暮らしていた時に作ったカセットテープが出てきた。なんと120分テープで、ただただ自分で聴くために作ったものだ。A面を聴き直してみた。以下。
Tenderness / Paul Simon
Hey Joe / Jimi Hendrix
Friends Again / John Sebastian
Shining Star / Earth Wind & Fire
Sitting in Limbo / Jimmy Cliff
Heart of Gold / Neil Young
Ain't Nobody's Business / Otis Spann
Icecream Cake / Jeff Beck Group
Bring it on Home Back to Me / Otis Redding & Carla Thomas
Miss You / Rolling Stones
Nothing Can This Change Your Love / Sam Cooke
Rudy to Messege / Specials
You Don't Love Me, Baby / Magic Sam
Jealous Kind / Joe Cocker
We Gotta Make Up / Spencer Wiggins
Woodstock / Crosby Stills Nash & Young
Tennessee Waltz / David Bromberg
Moondance / Van Morrison
もう持っていないものも何枚かあるな。
15:26:18 |
skri |
No comments |
TrackBacks
01 February
このレコードを聴くな その2
Van Morrison / Wavelength (1978)
2016年8月号のレコードコレクターズのヴァン・モリソン特集に原稿を依頼され、文章を書いたのであるが、その時に自分がもっている彼の全てのアルバムを熟聴した。その時の原稿は私の仕事柄と編集部の意図する違う角度、という事からモリソンに仕えたギタリストのことを書いたのであるが、折しも『It's too late to stop now』の再発やその未発表音源が発売されるという事で、あえて『Moondance』『Tupelo Honey』の初期作品を取り上げた。そして、大好きなアルバム『Veedon Fleece』のRalph Washに言及し、字数が尽きてしまった。実はもっとも良く聴いたモリソンは、『Astral Weeks』を別にすれば、その次の『a period of transition』から『Irish Heartbeat』なのだ。
モリソンの凄さに驚いたのが、何と言っても私の世代では何と言っても "ラストワルツのキャラバン" という方も少なく無いであろう。私もその一人で、その後にまず過去作品を中古盤で探したクチだ。なので、リアルタイムは『into the music』まで進んでいたのだ。ただ特殊な事情があって、私が大学時代に参加していた音楽サークルでは、もう82年頃だが、『a period of transition』がなんだかリアルタイムのように聴かれていたのだった。このアルバムのギタリスト、マーロ・ヘンダーソンについて先のレコードコレクターズで触れられなかったのは誠に残念であるが、『a period of transition』から『Irish Heartbeat』そして『Hymn to the Silence』は私のリアルタイムと重なり、モリソン自身が年齢的に最も脂が乗り切った、しかも過去のしがらみから開放され、のびのびしていた時期と感ずる。
が、そんな中、名作『a period of transition』と『into the music』に挟まれたこの『Wavelangth』はモリソンの駄盤候補に熱烈なファンでも一票を投じるであろうという作品だ。原稿執筆時も聴いたのだが、今回また何故か気になって聴いてみた次第だ。
モリソン本人は凄い。絶好調の発声。私が持っているアナログは1stプレスではないし、この時代のリヴァーヴ処理は気になるが、それでも生々しさは感じることが出来る。それは揺るがない前提だ。
あくまでも私にとってだが、結論を先に言うと、このアルバムはA1とB1は聴かなくて良い。そうするとかなり楽しめる。A2からの4曲は次のアルバム『into the music』に続くリラックスさ、そしてB2からの3曲はその後数作のスピリチュアルな雰囲気をわかりやすい言葉で投げかけているのだ。おそらくこの時代モリソンが出来るポップを具現化した作品であることは間違いない。
とは言えアレンジに難も感じる。A2、絶妙な軽さ。シンセとオルガンの併用も悪くないし、コーダもよく考えられてはいるが、だったらフェイドアウトは残念。A3、リズムは自然にアレンジされていて悪くないが、ギターリフは?というかダサイかな。そのボブ・テンチの待ってましたとばかりのオブリガードは脳内で消す。A5、リズムのレゲエ風味は時代を感じるが、リラックス度はピカ1。ガース・ハドソンのアコーディオンも良い。A5、コーラスアレンジにかなりの工夫、前作のドクター・ジョンの影響か? コード進行はピーター・バーデンスのテコ入れがあっただろうな。今ではそれはむしろ避けたい響きかも。でも良い曲だな。B2、その後のモリソンの道を示した名曲。クマ原田さんのベースが深く響き過ぎてキックとのバランスが良くないが、それがここでは吉。B3これも名曲。この曲だけ柔らかめの声にしたミックスあるいはマスタリングは吉。惜しむらくはテンチのプレイかな。この曲に限らず、既に始まっていたNew Wave時代、エレキギターの衰退を感じさせすぎるのだ。B4はこのアルバムの白眉。モリソンの代表曲と言っていいくらいの名曲でよく考えられている。ただB2では意図しない効果だっただろうベースとキックの関係はここではいまいち。バーデンスのピアノはキラキラしていて少し小賢しいが、まあ良い仕事で収めた。ガットギターの配置もグッと来るし、テンチのプレイもこのアルバムでは一番好感が持てる。そして、地味ながらハドソンのオルガンは流石。なによりモリソン節のメロディと歌い回しは唯一無二だ。
ちなみに聴きたくないA1はキラキラのピアノと決まりきったギターアレンジ、それだけで萎える。ハドソンのシンセソロの後半は流石だがミックスで押さえられて残念。B1これがアルバムタイトル曲だというのが、おそらく全ての元凶。この軽薄さ、ダサさがこのアルバムの悪いイメージなのだ。シンセのフレーズと被さるビートとギターコード全くワクワクしない。そして何と言うかMTV感だな。もちろんこの時代を考えればモリソン本人のソングライティングはそれなりに対応した2曲ではある。そう言う意味では聴く価値もまあある。
数年前、湯川潮音さんとの仕事でクマ原田さんとご一緒したことがあった。もちろんこのアルバムの録音時のエピソードも聞いた。クマさん参加曲は一曲一週間くらいかかったらしい。モリソンはスタジオで曲が降りてくるまでメンバーはひたすら待機させているいるとのことだ。ギャラは日数分貰えるので、クマさんは何の問題も無かったが、とにかく曲が降りて来た時のモリソンは凄まじく、何が起こったのか把握出来ないまま無我夢中で気がついたら一曲録り終えていたという。
とにかくこのアルバムはいろいろ文句もあるが、脳内でいろいろ差し引いたり、想像したりすると、かなり楽しめる。なによりそれをさせるのがヴァン・モリソンの存在なのだ。
02:12:24 |
skri |
No comments |
TrackBacks
19 January
このレコードを聴くな その1
Country Joe McDonald / LOVE IS A FIRE (1976)
今のレコード棚が完成して、かれこれ4〜5年は経つ。当初は余裕で収められていたレコード達もいつしか棚の中で窮屈になり、取り出しが困難になり始めた。レコード棚が完成した時から、並び替えた順番で暇をみつけては丁寧にクリーニングをして、収まった順番に全て聴いていくこと4〜5年。勿論断続的だが、ようやく半分くらいか。その間、処分したものも少なく無いが、やはり増えたものの数の方が多い様で、前述のとおり棚に全く余裕がない。なのでやはり自分にとって不必要なものは処分することを検討しているのだが、その前に何故それが駄目なのか、もう一度良く聴いてみようと思った訳だ。
Country Joe McDonald / Love is a Fire 実はこれまでも幾度となく、処分リストに上がったものだが、フェイバリット・ギタリストの一人 Ralph Washの参加作品という分かりやすい理由で、未だ手元にある。久しぶりに針を落としてみたが、やはりこりゃ酷い、が、どうやら今まで処分しなかった理由がWashの参加以外にも、何気なく感じていたことが明確になった気がした。
カントリー・ジョーというラジカルな、そしてウッドストックで名を馳せバスカーの逞しさを持つ男、その時代からかトリック・スター的な印象も無きにしもあらずな男、をいかに1970年代中期にビルボードチャートやラジオのパワープレイ、はたまた映画やドラマとのタイアップでポップスのプロの歌手に仕立て上げようという作りがとても興味深いのだ。
私が今所有しているカントリー・ジョーのレコードはこれとウッドストックに過ぎない。この直後のアルバムだったと思うが(Goodbye Bluesというタイトルだったか)ファンタジーでの3枚目は随分前に処分してしまったし、80年代後半のCDもかなり前に手放した。両方ともあまり良い印象は無いし、あまり覚えてもいない。が、今でも買おうと思っているのが、Country Joe & the Fish の1st。これはとある場所で聴いて、とても音が良かった記憶がある。あのフラワー・ムーブメントの中できちんと録音されたアルバムに感じたのだが、そんな発見してからもう十年くらいは経つか。
さて、この Love is a Fire は、まずジム・ゴードンのフィルで幕を開ける。ドラムの音がやけにタイトになり始める時代に差し掛かっている訳で、ここでもその影響は隠せないが、素晴らしく安心した音だ。プレイもアレンジャーの Jim Ed Norman が指定したであろういくつかの箇所を除けば申し分無い。が、これはこのアルバムの弱点をあぶり出していて、何気ないドラムのプレイと音に耳を奪われてしまうのだ。ジョー御代の存在はひとまず置いておいて、ベースのデヴィッド・ヘイズはこれまでの数々の名演の良さはここではほとんど発揮されていない。程よいリリースの的確なキックとのコンビネーションは悪過ぎる箇所が散見される。特に8分音符が2つ連なる箇所は本人の苦悩さえ見え隠れするようなもやもやさだ。ようするにゴードンはこのディスコ〜ニュー・ウェイブ的なものに自身の解釈で対応したのだが、ヘイズはそうではなかったのだ。そしてゴードンはドラムスのチューニングとプレイのクールさでこのアルバムに貢献したが、それとは別のアプローチで一役買ったのが地味ながらもラルフ・ウォッシュ。ウォッシュの参加曲はそう多くないと思われるが、エレキの音色はそのままにディスコ風味に貢献しているし、ほんの少ししか分からないが、やはり独特の間があり、アレンジャー指定のフレーズをユニゾンする時でもその発音は耳を惹く。1曲くらいウォッシュのギターソロが出て来ても良いのでは、とも思ったりしたが、このアルバムはどんな楽器のソロもほぼ無い。ノーマンとプロデューサーの Jim Stean がかなり仕切っていたことは想像に容易い。
たしかこのアルバムはファンタジーでの2作目だったかと思う。次作もファンタジーという事を考えれば、そしてカントリー・ジョー・マクドナルドというアメリカンロック界のそれなりのネームバリューという事も考慮すれば、この時代、契約金ありの3枚契約だった可能性もある。だとすれば、前作の売上は芳しくなく、勝負を賭けざるを得なかったのが今作で、そして数字的にも失敗。次作は「ああ、あれは俺の身の丈とはちょっと違っていたから、古い曲もやってみるか。もう契約も最後だし」なんてことを思ったのかも知れない。
ともあれ、もうちょっと細かく楽曲を探ってみようと、もう一度ターンテーブルに載せてみる。
まず冒頭、こりゃディスコだ、曲順としてはこれはアルバム一曲目しかありえないように感じるが、だからこその勝負。だがウォッシュの地味に奥深くミックスされた存在は一聴では分からないが、独特で悪くない。A2はノーマンのアレンジのダサさというか気負い過ぎだったのか。リズムブレイクがかっこ悪いしジョー自身も対応出来ているとは言いがたい。曲調としてはシングル候補だったのか。だが歌唱力に難ありだったのかコーラスアレンジはちょっと派手。A3、ここらで落ち着き、ということでカントリー調。唄も無理が無い。そしてストリングスアレンジはこのアルバムでのノーマンの最上の成果を聴かせる。A4、メロディに合わせたリズムフックが小賢しいがゴードンも無機質に対応しているのがまあ良いのか。ウォッシュであろうアコースティックギターが曲をもたせたが、何故この曲フェイドアウトなの? A面最後、こりゃポップだね。誰がカントリー・ジョーの是を望むのかとも思うが、ウォッシュも地味ながら良い仕事よ。
B1はドラムスに耳を惹かれる。ストリングスも良い。色々な意味でベスト・トラック? さあここでカントリー風味のB2、ペダル・スティールのフィーチャーだがウォルシュのリズムも吉。B3、きました、ニュー・ウェイヴ風味。ゴードンの対応力とR&B風味のホーンでとばしたいところをついつい聴いてしまった。B4は爽やかな良い曲の感じがしたが、唄は良くないし、がBメロでちょっとずっこける。でもストリングスとコーラスのアレンジはよくやったよ、ノーマン。そしてB5はディスコ。サビは当時のキャッチーさを反映していて良い作り。ホーンもコーラスも良い。さりげないコンガも良い効果だ。ギターはかっこ悪いけど、当時のヒット曲と考えればこういうのはあったよね、という感じ。ただちょっと長いかな。
あえて書くが、どの曲も詩が酷い。ストレートなラヴ・ソングなのだが、気の効いた表現は一切ない。ラジカルなカントリー・ジョーのイメージを逆手に取っているのか、とさえ勘ぐりたくなる程に愚直なのだ。
私にとってはカントリー・ジョーは魅力のある歌手ではない。音程や声質等そう言うことを言うつもりは無い。このアルバムでは惹き付けられる歌ではないのだ。が、どうにかしようという、熱量は感じられなくもない。が、それ以上にどうにかしようと頑張った(失敗の部分はあるにせよ)アレンジャーのノーマンとプロデューサーのスターンの熱量は伝わり残念だったアルバムの裏の努力も垣間見える。頑張ったけど失敗した職人の仕事なのだ。
そして極めつけは、ミックスのAl Schmitt。さすがのシュミット。プレイにちょっと難があったヘイズのベースをさりげなくし、ゴードンの音をタイトでありながら響きも最小限生かす。そしてディスコ〜ニュー・ウェイヴ感も醸し出しつつの落ち着き。これは見事。
それほどの職人芸でも失敗作はそこそこあり得るのだが、よく聴くとその辺りが手に取るようにわかる、という作品もそう滅多にあるものではない。そう言う意味では、もう少し手元において置こうとも少し思ったが、そんなことでは一向にレコードは減らないので、処分棚に収めることにしよう。
そうだ、音質という事で言えば、私が聴いているのは1976年発売のビクターの日本盤の見本盤。この頃の日本盤見本盤は音が良いのだ。中にはアメリカ盤よりよいと感じるものも少なく無い。こんな失敗作と思えるものでも、深聴出来たのにはそんな所為もあったのかも知れない。それはともかく、とにかく人が思いをもって作ったものには良い悪いではなく、何か特別なものが記録されていることがままあるのだ。そして、カントリー・ジョーはこのアルバムの後にローリングココナッツレヴューで来日したんじゃなかったかな。私が足を運んだのは初日のジョン・セバスチャンやフレッド・ニールだけだったので見られなかったけど。
中学の時の担任は国語の専門だったのだが、一度、授業ではない時に「太宰治なんか読むなよ」と言った事があった。と言われれば読みたくなるのが中坊というもので、私はその頃かなり太宰を読んだのだった。
04:23:13 |
skri |
No comments |
TrackBacks